キリンソウと四季の彩り日記屋上緑化システム株式会社
技術顧問 山下 律正
酒を電気分解で促進醸造する技術 第1回 97年前の忘れ去られた技術
日本で電気分解による促進醸造技術が民間発表されたのは、97年前であり、前年の昭和3年には昭和天皇の即位の礼(11月10日)が挙行され、昭和4年と言えばソ連・スターリンの独裁政権スタート(1月31日)が始まった年に当たる。
1973年私が近畿大学に入学した年が事の始まりである。高校は岡山県で最も創立が古い3校の歴史がある勝間田農林高校、多くの偉人を排出してきたが、大学への進学では、専門高校からの入学であり教育課程の学力差は普通高校からの入学生に比べ如何ともし難く、多くの先輩方も同様の悩みを抱えての入学であり、以前より先輩から新入生の面倒を見るべく、高校から大学在校生に面倒を見るように連絡が届く仕組みがあり、在校生が勉学に励める環境を提供する様に歴代先輩が手配してきた。その一環で、入学生は少しでも専門勉学・技術を得る為に学科直属のサークルの農芸化学研究会に強制的に在籍する事となる。この研究会は農学部全学科の研究室直属のサークルであり、教授や助教授の研究の手伝いや4年生の卒論の手伝いをする、学部が好きで入学した一般の生徒も多く在籍していた。
入学時の農芸化学研究会は100人近く在籍し大学の一学科の定員より多い人数が在籍していた。1年当時から研究室を出入りでき4年生の実験を手伝う事ができ、助教授が直接指導する独特の仕組みを作っていた。先輩より雑学の中で戦時中の醸造技術の一つとして興味ある話を聞いたのが始まりになる。「酒を電気分解すると旨くなる」聞いた時には、電気分解しても発生するのは酸素か水素が気体で、副反応でエステル結合が香気を発生すると思ったが、酒や味噌に代表される「熟成」には複雑に理屈では説明のできない反応が起きる事を思えば可能性も有ると酒の電気分解法に興味を持った。
さらに熟成について調べると、醸造品が盛んな日本では、より旨い食品への追及は古い時代より盛んに行なわれていた。当時大学図書館で見た本には戦中前の食糧難の時代にいかに合成清酒を造醸清酒に近づけるかの試行錯誤の方法が紹介されていた。超音波、高周波、電気分解、遠心力など思い付く方法が書かれそれなりの成果も紹介されて、美味い物を作る追求心に感心したことを戦前の物資も技術も乏しい時代に書かれた成果を紹介したページを今も思い出す。
見つけた古い食品醸造学の本で本当に当時促進技術が存在するかを調べてみると、確かに第2次大戦中の代用促進醸造法として電気分解技術が記載されていた。さらに超音波促進法を含め、酒、醤油、味噌などの発酵食品も含め代用品製造法が数多く紹介され、こんな事までしてとにかく旨くして食べる事に傾注したかと人知の深さに感心させられた。そこで身近にあるバッテリー充電機と近くにある銅板やステンレス板を使って実験を開始した。電極板には電離させるイオン化傾向が離れている金属を使って、手製の装置を作り酒の電気分解を試してみた。
美味い酒といえばウイスキーではオールドが一番に浮かび、安い酒と言えばレッドであった。手始めに飲んでいたサントリーウイスキー・レッドを使って試した。単独で電気分解すると口当たりが良くなり、のど越しの辛さがソフトになりウイスキーはまろやかになり飲みやすくなった。ただし、電極板香りも発生し電極を何とかしないと実用には遠い事が判る。
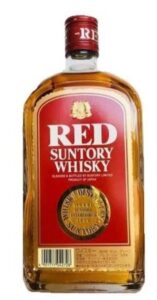
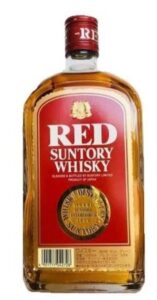
喜んで次にしたのが、ウイスキーレッドにサントリー・オールドを少し混ぜ電気分解する事だった。
ウイスキーの醸造も古い樽を使い醸造を促すと聞いたことがある。電気分解も醸造が進んだ高級なウイスキーを混ぜる事で、促進造成される過程で香りが熟成を促進させ良くなるのではないか想定した試験であった。
結果は単独で電気分解するより混合する方が香気の発生は進み、のど越し香りがオールドに近くなって喜んで作っていたことを思い出した。
当時電気分解で起きた促進醸造の仕組みは、アルデヒドなどの分子量が低い分子が、電気泳動の中でエステル反応を起こし風味とまろやかさを促進したのではないかと思っていた。このような低分子量分子を高分子量分子やエステル化反応を実現できるのであれば、養生が必要な食品には全て応用できるのではないかと期待を大きく膨らませていた事を今でも思い出す。
次回は合成酒が歩んできた歴史を紹介する。
屋上緑化システム株式会社
技術顧問 山下 律正
新着記事
25年前の薄層屋上緑化システム 公共展示場に見る2000年当時の薄層屋上緑化
化学突然変異育種 実験講座”12 突然変異試験に最適な時期と準備
キリンソウ・セダム屋上緑化の「冬支度と冬の管理」
キリンソウ、セダム類の屋上緑化・壁面緑化 春と秋の挿し芽増殖方法
キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 甲虫害編
キリンソウ・屋上緑化・壁面緑化 秋のメンテナンス 肥料編
屋上緑化の源風景 災害から屋根を守る知恵が育んだ「芝棟」
四季彩4 キリンソウ 総合技術カタログ A new variety, Shikisai 4 Kirinsou,General Technical Catalog
常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第5回 キリンソウの常緑とは?
常緑性キリンソウ「四季彩4」 種苗登録認定 特性解説 第4回 根が露出し裸の状態で、酷暑・防風・豪雨に負けない耐久試験



